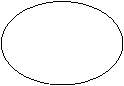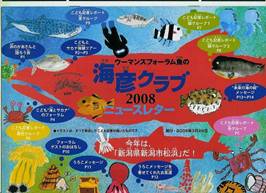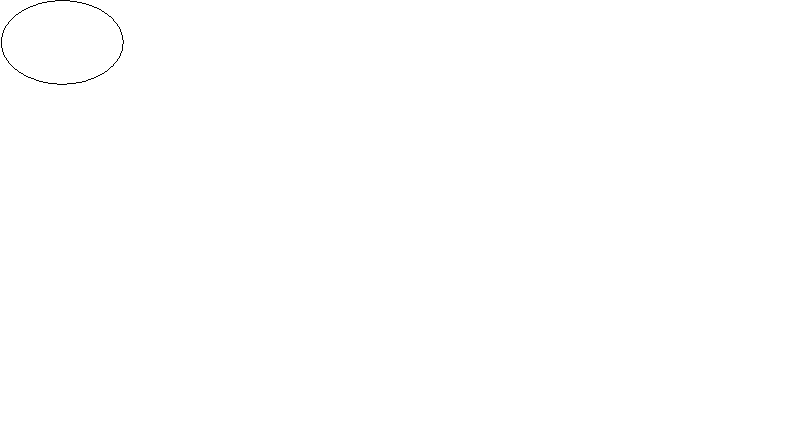�@�@�@�@�@�@ �C�F�N���u�@�@�@�@�@�Q�O�O�X�N�P��1�Q���i���E�j)�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@ �@ ����ǂ��E�C�ƃT�J�i�̃t�H�[������J�ÁI ����̃e�[�}���T�P�B���{�l�ɂƂ��đ�ȋ��ł��B���܂������A�S���ŐH�ׂĂ��܂��B �u�ǂ����ăT�P�́A�̋��̐�ɂ̂ڂ�Ȃ��Ȃ����́H�v�u�T�P�̂Ӊ����āA�ǂ�Ȃ��ƁH�v �C�F�N���u�̂��ǂ������́A���C�ɐV���ł̎�ސ��ʂ\���Ă���܂����I ���ǂ������̋������т��܂����u�j���[�X���^�[�v�����ЁA�������������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�C�F�N���u�Q�O�O�W�v�@�P�N�Ԃ̊����̋L�^�@ �Q�O�O�W�N�P�O���S���i�y�j�A���c�J�旧���u���w�Z�Łu�l�̂�������ƌ�낤��v���J�ÁB �l�̂Ƃ�����A�����������B�������A�傫�ȃT�P���B�z�[���ŐV���̗��j��T�P�̏���ʁA�V���ƃT�P�� ���������w��ł���A�ƒ�Ȏ��ցB�T�P�̃I�X�ƃ��X�̌���������ؑ��g�����ɋ����Ă��������A�T�P�̂� ������̌��B�傫�ȋ������ɁA�����ł邵�A��������яo���܂��B�ڂ��Ԃ�q�A�����o���q�ǂ������܂����A �������̂��̂������������Ď������͐����Ă���Ǝ����B�E�C���o���ďo�n����ɂ���A�T�P�������܂����B �Q�O�O�W�N�P�O���Q�W���i�j�A�����旧�؍��쏬�w�Z�Łu�l�̂�������ƌ�낤��v���J�ÁB �V�����V���s�̏��l����A�l�̂Ƃ�����A�������A�傫�ȃT�P�������Ă��Ă���܂����B �C�F�N���u�Q�O�O�W�̂Q�Z�ڂ́A������̖؍��쏬�w�Z�B�T�E�U�N�����Q�������������T�P�������w�т܂����B �����l�̋��������l�A�{�Ԃ������I�@�����`���A�C�N����H�ׂ����Ă��ꂽ�I�@��������Ă��́A���Α�\���搶�� ����L�̂Q�̎��Ƃ̂̂��A���ǂ������͍앶�������A�S���̂Ȃ�����Q�R�l�̂��ǂ��L�҂��I��܂����B �V���s�E���l�ւ̎�ރc�A�[�̂悤���́A�����́u���Y�^�C���X�v���������������B
�@�@�Q�O�O�W�N�x�ɊJ�Â����A���ǂ������Ƃ̊����̋L�^�@ �P�O���P�W���i�y�j�A�O��s����Y���w�Z�Łu��U�V��l�̂�������ƌ�낤��v���J�ÁB �����͖k�C���E�m�����̂�������B�쑾���m��������W���[�i���X�g����ނɗ����I �k�C���m�����̕l�̂Ƃ�����A�������}�R�K���C��z�^�e�������Ă��Ă���܂����B �~�N���l�V�A�A�g���K�A�p�v�A�j���[�M�j�A�̋L�҂����{�̋��Ƃ���ނɗ������܂����B �E�[�}���Y�t�H�[�������̊��������ЂƂ��������Ƃ������v�]�ɂ������A�O��s����Y���w�Z�Ɩk�C���m���� �̂����͂āA�}篁u�l�̂�������ƌ�낤��v���J�ÁB�R�J���̐V���A�z�[���y�[�W�ŏЉ��܂����B ���R�J���̋L�҂ƕl�̂�������i�Z�����j�@�@���l�̂Ƃ����}�R�K���C�������I�@�@�@�@���m�����̘e�{�������삯���ăX�s�[�` �@�@�P�P���W���i�y�j�A�����s�Ƃ�������ɑD�̉Ȋw�قŁu���m�����t�H�[�����v���J�ÁB �Q�̏��w�Z�̂��ǂ��������A���m�����ɂ��ė��h�Ȕ��\�����Ă���܂����I 10���AWFF����̑�w�̐搶���i�n�����猤����̏��R���闝�����ƒJ�쏮�Ɨ����j�ɓ����s���� ���w�Z�Łu���m�������Ɓv���s���Ă��������܂����B��u�������ǂ��̒����琙���旧����ˏ��w�Z�̂T�N�� �`�[���u����˃t�B�b�V���v�Ɩk�旧�����w�Z�̂T�N���`�[���A�u���m������邭��v���P�P���W���A ���\�ɗ��Ă���܂����B�܂��T���S���m�̊����n�����i������w�j�⍑�ۖ@�̉��X���N�F�y�����i����� ����w�j�AWFF�̔������q��\�A�t�[�h�R�[�f�B�l�[�^�[�̒��J����搶�ɂ��p�l���f�B�X�J�b�V�����A ���m�������ӂŊl�ꂽ�����i�q���W���}���U�C�E�I�Ȃǁj���g�����������̎��H��Ȃǂ��肾������I
�����m�������Ƃł͓��{�̊C�̌`���w�ԁ@�@�����ǂ������������m�����̈Ӌ`�\�@�����܂��܂Ȋp�x����ӌ����q�ׂ�u�t
�@�@ �N�W���́@�@�@�@���N���S���e�n�Łg�N�W���Ɠ��{�l�h�̊ւ����l����C�x���g������܂��B �C�x���g�@�@�@�@���߂��̂����A���S�̂�����͂��ЁA���Q�����������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �����ւŃN�W���̑D�����w���悤�I�i2009�N�S��25���i�y�j26���i���j�j �u�~�ޕߊl�����D�c��ʌ��J�v�i��ÁF�i���j���{�~�ތ������A���{�ߌ~����A�����D��������Ёj �@�@�@�S��25���i�y�j9�F00���T�@10�F00�|16�F00���J�@26���i���j8�F30�|16�F00���J�@�@�Q������ �@�@�@���֍`���邩�ہ`�Ɗݕǂɂ����āA������D�u���V�ہv�A�ڎ��̏W�D�u���E�V�ہv�̑D������ʌ��J����B �@�@�@�܂��b�ɂ����Ē����T�v�̓W���A�N�W���O�b�Y�̔̔������{�B �@�@�@25���i�y�j�ɂ͉��փO�����h�z�e���ɂ�����17�F00�`���v�搶�ɂ��L�O�u������J�ÁB �����H�ŃN�W���̗��j�E�������w�сA���ꂩ����l���悤�i2009�N�H�\��j �u�S���~�t�H�[����2009 in ���H�v�i��ÁF���H�s�A���H�����狦�c��ق��j �@�@�@�@�S���e�n�̃N�W���Ƃ䂩��̐[���y�n�łQ�O�O�Q�N���烊���[�J�Â��Ă����C�x���g�B��N�̒��茧�V��ܓ����ɂÂ��A �@�@�@�@���N�͋��H�s�ŊJ�ÁB���₢���킹�͋��H�s���Y�ہi�s�d�k�D�O�P�T�S�|�Q�Q�|�O�P�X�P�j |
||||||||||||||||||||||||||||||||
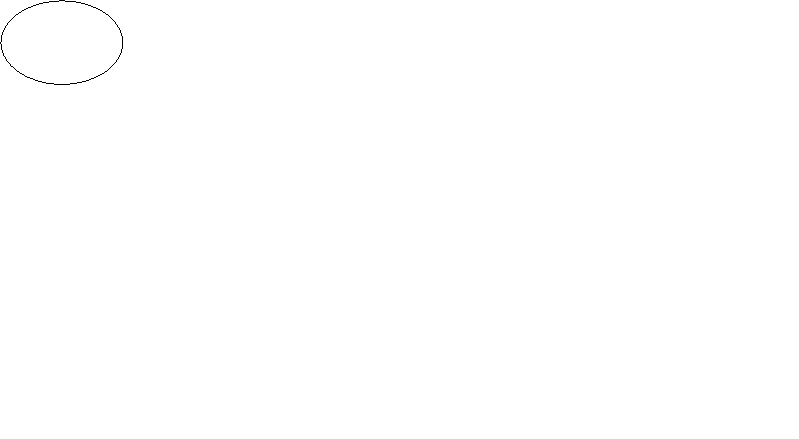 �@���҂����ˁI ���N�́u����m�v�́A�W���W���i�y�j�Ɍ��܂�܂����B
�@���҂����ˁI ���N�́u����m�v�́A�W���W���i�y�j�Ɍ��܂�܂����B
�C�x���g�@�@�@�@�H�����w�҂́u���v�搶���m���߂Ă����������B
���@�@�@�@�@�Q�O�O�S�N�ɃX�^�[�g���A���N�łT��ڂ̃T�}�[�Z�~�i�[�ł��B
�@�����e����ɂ��ẮA���ݏ������ł��B���킵���͎����ł��ē��������܂��B
��N�x�̒z�n�{�莛�ł̍u���́A�����̒z�n�s�ꌩ�w����܂ߑ�D�]�I���N�̃N�W�������ٓ��A
��N�̒z�n�����ٓ������킢�[�����̂ł����B���N����������炵�Ă܂���܂��B��A�����ҁI
 �@
�@ �@
�@
�@�����N�̃N�W�������ٓ��@�@�@�@�@�@�@�����v�m���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����N�̓p�l���f�B�X�J�b�V������
|
�����ǂ���@���{�̋��ƁA�����̕�炵�A���H�����̗��j�����́A���l�ɂ���܂��I �@�@�@�@�@�@�@���́A�{�{��ꂪ���ŕ����ďW�߂������������ɁI �@3��13���A�������q��\���i�Ɓj���Y���������Z���^�[�E�������Y�������i���l�s�����j�̉^�c��c�ɊO���L���҂Ƃ��ďo�ȁB�����Ŏ����ǂ����s���܂����B�����ǂ̖ړI�́A���������}�����������ւ��25���_�̋��Ǝ����ł��B���a24�N����U�N�����đS���̕l������W�����u���Ɛ��x�����v�̌Õ����ƕM�ʍe�{�i���L�҂̋����ĕM�҂������́j�A�܂�����E����ɂf�g�p�̐�̉��łǂ̂悤�ɋ��Ɛ��x���\�z���ꂽ�����L���������ȂǁA���{�̋��Ƃ̗��j�╶���ɊS�����҂ɂ͂܂��ɕ̎R�B�����w�ҁE�{�{���炪�S���̕l������ďW�߁A�M�ʂ�������������܂��B����N�W���̊G�̋L�^���B�ߐ�����ߑ�ɂ����Ă̋����̐��x�Ɋւ��镶���́A���ƂƓ��{�l�̊ւ�����̓I�ɓ`���鎑���Q�ł��B�܂����̓W�����ق́A���܂��܂ȋ��ނ̂͂����⋙�Ɩ͌^�A�y�����H�i�T���v�������肾������B���J�ɂ����������������c���ْ��A�i���̗����ɐS���犴�Ӑ\���グ�܂��B �@�}�������ق̊J�َ��Ԃ͕�����9�F30�`12�F00�A13�F00�`17�F30�B��ʂ́A���l�}�s�u���i�w�v�������V�[�T�C�h���C���ɏ�芷���u�s���w���w�v���ԂT���B�i���₢���킹TEL�D045�|788-7608�j |
||
|
|
|
|
|
�����̂�����ɂf�g�p�������A�Ɛ����@�@�����a16�N�A�k�ɓ_��ڎw�����j�������@���W�����ق����ē����������� |
||
|
�Ⴈ�\�����݁A���₢���킹�͉��L�܂Ł� �C�̍K�Ɋ��ӂ���� �E�|�}���Y�t�H�|������(�v�e�e)������ �����s��������3-12-15����גJ�r���S�e�@���P�O�S�|�O�O�U�P TEL.�O�R�|�R�T�S�U�|�P�Q�X�P�@FAX.�O�R�|�R�T�S�U�|�P�P�U�S E-mail�@gyo��WFF.gr.jp�@�@http://www.WFF.gr.jp |
|
�v�e�e���^�|�m��.�S�W �@�@�Q�O�O�X�N�@�S���P���@�@�@�@ �ҏW�F�����@���I�q �B�e�F�����@���� |